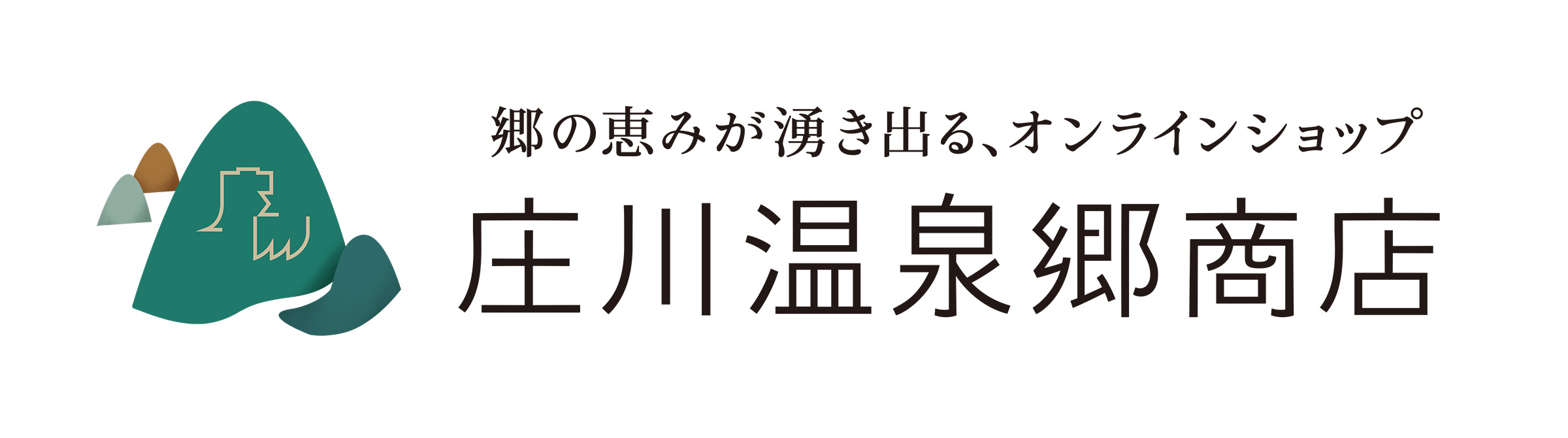越中三助焼
越中三助焼 庄川ゆず
庄川ゆず 庄川おんせん野菜
庄川おんせん野菜 庄川挽物木地
庄川挽物木地 山菜
山菜
買って楽しむ庄川温泉郷
庄川ゆず

日本国内最北限で栽培される庄川ゆずは「金屋ゆず」の名で古くより親しまれており、その原種は弘法大師によってこの地に広められ、のちに巡錫に訪れた釈如上人を敬い、住民がこれを献上したとも伝えられています。他の産地のものと比較して表面が粗く凹凸が目立ちますが、ゆず特有の香気をたっぷりと含み、果肉も厚く酸味の強い特上品です。
取扱店舗
庄川おんせん野菜

「庄川おんせん野菜」は、庄川清流温泉の源泉水を肥料として与え、育てられた野菜です。
トマト、小松菜、カブ、キャベツ、ショウガ、シュンギクをはじめ、様々な野菜が育てられています。
取扱店舗
山菜

庄川峡の雪が溶けだすとともに、山々には様々な種類の山菜が芽を出し始めます。
4月中旬から5月中旬が最盛期となり、各家庭の食卓や料理店にはそれぞれ趣向を凝らした山菜料理が並びます。
取扱店舗
工芸品
庄川挽物木地(しょうがわひきものきじ)

天正年間(1573~91年)から庄川地域は北陸における木材の一大集積地でした。
その豊富な木材を求めて慶長2年、木地師の越後屋清次がろくろ木地を営んだのが庄川挽物木地の始まりと伝えられています。
庄川挽物木地は横ろくろを使用し、横木材を材料に挽物をするのが特徴で、年輪が様々な形となって現れ、独特の濃い色調が木目を引き立たせています。
取扱店舗
越中三助焼(えっちゅうさんすけやき)

富山県砺波市の福山丘陵一帯は陶土に恵まれ、古くは奈良・平安時代の須恵器に始まり、生活用具と瓦の製造が行われていました。
この瓦製造の一軒であった谷口三助(嘉永元年~明治38年)とその長男、谷口太七郎(明治7年~昭和8年)が瓦製造の窯で壺、鉢、皿などの生活用具を作り始め、三助焼の基礎を築きました。
恵まれた土地から取れる土を用い、この土地が生み出した草木から釉薬を作り、すべての工程を手作業で行っています。
中でも代々受け継いだ、淡く深い緑色の釉薬が特徴です。
取扱店舗